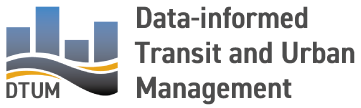1月21日(火)、東京大学モビリティ・イノベーション連携研究機構 (UTmobI) に設置された社会連携研究部門、データインフォームド都市・交通学(DTUM)が主催するセミナー「データを活用した未来のまちづくりに向けて~多様性を見つめ、市民中心に考える~」が開催された。
登壇者は東京大学大学院情報学環 澁谷 遊野 准教授と、アクセンチュア株式会社 執行役員 海老原 城一 氏。
講演後のパネルディスカッションでは、澁谷准教授、海老原氏、そしてモビリティ・交通分野のコンサルティング会社AMANE代表で司会を務めた井上佳三氏が多方面にわたる意見交換を行った。

所属企業を超えて一つの目標へ 会津でできる理由
――会津若松のスマートシティを運営するAiCT(アイクト)コンソーシアムには、96社もの企業が集結し14のワーキンググループが立ち上がっています。ともすれば競合もする96社間間の相互理解はどのように形成するのでしょうか
海老原氏「『他の地域で競合しても会津若松では競合しない』ということが大前提になってっています。全国で競合しないという前提だと誰も参加できなくなってしまう。一方で、デジタル基盤の全てを一社で立ち上げるというのは、デジタル時代には非効率な上に費用もかかりすぎる。そこで会津若松の新しいインフラ共創領域では戦わず、よそで競争するという発想の転換がありました。これが成功すればよく言う『競争と共創』もうまくいくのではと思っています」
海老原氏「企業同士が、正式な理事会で月1回、その他にも週1回くらい顔を合わせて議論できていますが、これが非常に重要だと思います。アポを事前に取らなくてもAiCTという建物に行けば、企業を超えて誰と話ができると環境は、日本企業が苦手とされる『所属企業を超えた話』ができる会津若松の本当の良さだと思います」
――そうした現状にたどり着くまで一番のハードルは何でしたか
海老原氏「市役所の中で積極的に取り組みを推進してくださる方々がいて、その方々と一緒に進めていこうと決まったのが会津若松での取り組みを始めて1~2年目くらいのことでした。それれは非常に大事だったのかなと思います。チャレンジングな目標を掲げたときに、行政の担当者がある意味リスクを取って勝負をするのはそう簡単ではないと思うんですよね。しっかりと市民を守らなければければいけないので、安易に一時的なアイデアに流されるのも良くないですし。他の地域と比べても、もしかしたら一番難しいハードルを早期に越えていた可能性があります」
ユーザー増「トライ&エラー地道に」 複数のニッチサービスから始め、徐々に公益的に
澁谷准教授「海老原さんはさまざまなサービスを実際に展開されていて、大変勉強になりましたし、更に知りたいと思いました。その中でも、サービスやシステム、連携体制の形が出来上がった中で継続して人の参加を促す、データを回収していく上でのご苦労を詳しくお伺いできますか」
海老原氏「AiCTコンソーシアムに参加している企業の担当者は、それぞれの所属企業から『何年後に利益が出るサービスを作るのか』とプレッシャーをかけられています。しかしユーザーの数もデータの数も、もっともっと増えないとマネタイズできないんですね。そこは96社全員が同じ目標に向かっていて、それぞれの領域で人を増やす努力をしています。お祭りをしたり小中学校に授業をしに行ったり、その人がすぐユーザーにならなくても若い人が地元のスマートシティづくりに関心をもったり、子供たちが家で保護者に話してくれるかもと思い、トライを続けています」
――そうした学生や子供たちとの関わり合いを十何年していると、若い人が社会人になって、取り組みを応援する市民も増えているのでしょうか
海老原氏「そうですね、2015年にシステムの原型ができ始めて10年たち、アーリーアダプター※が『スマートシティサポーター』になったり、友人に推薦してくれたりしています。その次、やはりマジョリティに使ってもらうという最大のチャレンジに向かっている感じですね」
※ アーリーアダプター:「イノベーター理論」において、新しい技術・製品を比較的早い段階で採用する層。イノベーター(2.5%)>>アーリーアダプター(13.5%)>>アーリーマジョリティ(34%)>>レイトマジョリティ(34%)>>ラガード(16%)
――ユーザー増加とサービスの網羅性は相関関係にあるとご説明をいただきました。どのような考え方で市民のIDを増やすための取り組みをしていますか
海老原氏「トライアンドエラーで少しでも増やすことを地道に繰り返しています。半強制的に参加してもらうような形だと、一瞬ユーザーが増えても、離脱する人も多い。北風と太陽じゃないですけれども、本人が使いたいと思って入ってもらえるというのは大事だと思います。ただ、多くの方のニーズに応えようとするとだんだん丸まって当たり障りのないものになってしまう。『特定の人にはいいけれども、使わない人は使わなくてもいいよ』というサービスをいくつか作っていくのが初めのころのアプローチでした」

「失敗許される会津」から事業を大きく、成功へ
澁谷准教授「データの生成も含め、小さな取り組みの失敗(エラー)を許す環境は、地域の取り組みを成功に導く上で大事だと思っています。リスクを負う覚悟を決めないとできないことは多いのですが、ある程度失敗も許容されて試せる環境を地域に作ることが肝な気がしています。なぜ会津若松では失敗が許容されるのでしょうか」
海老原氏「会津若松はと実証の場所なので、失敗したらやめてもいいということになっています。実際に、色々な企業がトライした取り組みをやめています。3万人ぐらいの基盤というのは、いきなりゼロから始めるよりもいいスタートを切れる可能性もあり、かつ失敗できるサイズ感です」
海老原氏「ただし、そのサイズではビジネスの成功もありません。なのでうまくスタートして、ある程度成功の兆しが見えたら広めていくことが必要です。それができるようデータ連携基盤を先に広げているんですね。福島県ではもう人口ベース3分の2の地域で同じシステムが稼働できる状況で、企業からすると、非常にやりやすい環境が整いつつあると言えると思います」
海老原氏「増えるからこそ、より多くの人に価値のあるサービスを作っていけるということでもあると考え、トライしたいなと思っています。例えばオンライン完結の行政手続きが始まっても、窓口を全部閉めはしません。3分の2がオンラインにしてくれたら1人が3倍の時間、窓口で相談を受けてもらえることになります。デジタル化は使わない人にもメリットがある。そのことを考え、上手に説明する必要があります」
海老原氏「去年は100%デジタルの地域商品券をやっていただきました。1万円を出したら1万2500円になるという具体的なキャッシュバックがあるので、多くの市民が参加しますよね。市役所としても、ID数が多いのでこれはある種公益的なプラットフォームとして、100%デジタルで商品券を配ることになりました。これが例えば、100人しか使っていなければ、公益的なサービスとは言えなくなってしまいます」

澁谷准教授「今IDが市民の3割ということで、何割を超えたら公益性というか、地域全体にメリットが広まるかみたいな感覚値でも、ぜひあったらお伺いしたいです」
海老原氏「具体的な数字は難しいですが、アーリーアダプターといわれる人までをカバーする割合(約16%)は最低限必要とは思っています。ただし、16%ではまだ『一部の人がやっているだけ』の値だと思います。会津若松では、IDカバー率が3%くらいのときから『3割くらい超えたら公益的になるのではないか』ということを市役所と会話しており、ようやくその数値に近づき、超えてきたという感触があります。科学的根拠はないので、ぜひ先生にお示しいただければと思っています」
行動変容を促すのではなく、市民が望む方向を可能にする
――IDカバー率が増加すれば、地域の巻き込み方や、行動変容という観点で何かが変わってくるのでしょうか。
澁谷准教授「行動変容という話題はキーワード的になっていますが、例えば行政とか研究者が人の行動を変えてやろうなんていう発想そのものが、上から目線でおこがましいと思うんですね。どのようにより良い都市空間とかサステナビリティとか全体としての行動を良い方向に向けていくのか、上からではない目線でのデザインを深掘りし直すことが必要だろうと日々感じています」
澁谷准教授「そういう意味で本日の会津若松のお話を改めて聞いて、同じ場所で色々な方の顔が見えるということの重要性を探ってみたいなと、感覚的ですけれども気づきをいただきました」
海老原氏「行動変容っていうのは、文字通り、行動が変わるということでしょう。意識改革のようなものが行動変容と似ているなら、人の意識や価値観を変えるのは絶望的に難しいなという気がします。でも、例えば私が触れたHEMSの話、元々電気代を安くしたいと思っている人に電気代が全体の何位かを意識できる仕組みがあれば行動が変わるのは割とストレートですよね」
海老原氏「こうした意識改革をしない、例えば通勤時間を短くしたい人に、いつもこの道を行っているけれども、あっちの道の方が空いているよと知らせてあげたら変わるとか、そういうのはあるかもしれませんね」
課題起点とデータ起点の融合
――海老原さまから見て、澁谷先生の取り組みのなかでご興味のあるところは何ですか
海老原氏「先生方のデータ分析をお伺いして、会津でもやってほしいなと思うというのが、第一印象です。民間ベースで実装しているものは、リアルではあるけどもっと分析したら価値が出るのにもったいないと思われるのかなと感じます。一方で、当然研究からスタートするものというのは、研究のためにモニターを集めサンプルをとるアプローチが多いと思うので、そのどちらかに偏らず融合していければいいと思います」
海老原氏「困っている人のためのサービスを考えるときに、人間の能力では限界があります。例えば、バスが廃止された地域で免許返納した人が病院に行くという課題があれば、オンデマンドバスを病院予約と紐付けて予約しようと発想できます。一方で関連するデータがあれば、本来はデータ起点でのサービス設計もあるはず。課題とデータのそれぞれから出発してサービスを考えることができれば相乗効果があるはずです」
澁谷准教授「ご指摘の通りです。まとまったデータがあると、解析、シミュレーションや、いろいろなモデリングがしやすい。一方で我々は、コミュニティに所属する人が、どのようにデータの価値に気づいてコミュニティ内のデータを活用していくかという観点からも研究をしています。データの解析だけでなく、価値をいかに高めるかというところで、研究と実務の重なる点を見つけて市民協働的な観点から取り組みたいと思っています」
澁谷准教授「おっしゃるように最初からデータ収集を目的にすると絶対にうまくいきませんので、最初はニッチな、本当のコミュニティの課題に合わせたところから始め、ある程度データが集まったところで、それを活用してより良いサービスを考えることもできると思います。一方でせっかくサービスを作るのだったら、データをどう集めるかといった初期段階から、将来的にはデータを活用できるように、ある程度システムに埋め込むなどを考えることができたらWin-Winなものになると考えています」
個人も企業も「一緒に行動のインセンティブ」で地域を良くする
――データを活用で目指されるところを最後に一言ずつお願いします
澁谷准教授「いろいろな観点があると思いますけども、やはり1人では研究もできないし、地域の課題解決とか良いことはできないので、いろいろな方と連携させていただきながら、何かできたらいいなと思っています。そういう意味では現在阪急阪神ホールディングスさんとも研究でご一緒させていただいておりますが、今後いろいろと連携しながら、地域に還元できる研究をしたいと思っております」
海老原氏「地方では人口減少は避けられない中で、それをどれだけ食い止められるかが課題だと思います。そのときに同業者がいがみ合っていては、データもたまらないし、結果的に他の地域を利するだけ、あるいは特定のテック企業依存につながります。地域が儲かれば自分も儲かるという感覚、昔はそうだったのかなと感じるんですが、それを思い出してほしいですね」
海老原氏「今の社会は、僕らの人生50年ぐらいの中でもだいぶ変わってきています。地域でのおすそ分けや、隣に住んでいる人と情報共有して防犯していた時代から、マンションの隣に住んでいる人の顔も知らない状況になってしまっています。もう少し企業でも個人でも、上手く一緒の夢を見て、一緒に行動することが自分のインセンティブになるということができればいいなと思っています。それをうまく表現できたり、サービスで成果に繋げられたりすれば社会が変わってくれるのかなと思っています」
パネルディスカッションの動画は下記をご覧ください。