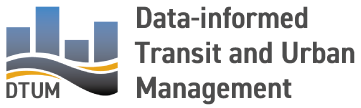1月21日(火)、東京大学モビリティ・イノベーション連携研究機構 (UTmobI) に設置された社会連携研究部門、データインフォームド都市・交通学(DTUM)が主催するセミナー「データを活用した未来のまちづくりに向けて~多様性を見つめ、市民中心に考える~」が開催された。
登壇者は東京大学大学院情報学環 澁谷 遊野 准教授と、アクセンチュア株式会社 執行役員 海老原 城一 氏。
アクセンチュア株式会社 執行役員の海老原城一氏は「会津若松における市民を中心としたデータ駆動型スマートシティの取り組み」の演題で講演した。
海老原氏は2011年以来、同社の復興支援プロジェクトを率い、福島県の会津若松市でスマートシティづくりに取り組む。現在は、スマートシティ運営組織AiCT(アイクト)コンソーシアム代表理事も務める氏は全国へ広がる「会津若松モデル」を解説した。
震災復興の新産業スマートシティでつくる
海老原氏と会津若松市の関わりは2011年の東日本大震災後、アクセンチュアがプロボノで始めた復興支援プロジェクトから始まった。
その後、震災で被害を受けた地域をどのように復興させていくかについての議論を重ねる中で、スマートシティプロジェクトへ発展した。
会津若松市は水力発電をはじめ再生可能エネルギーの種類が多岐に渡り、ICT専門大学である教育に力を入れている会津大学や複数の総合病院を擁しているなどの長所に着目し、企業にとって以降より必要性が増してくるICT人材が活躍できるような「雇用」の創出を目的として、データを活用した産業創出とスマートシティに取り組むこととなった。
その際、世界各国で取り組みが始まっていたスマートシティの基本計画を青写真にしつつ、会津の特徴を生かした形で計画を仕上げることにした。
その結果、地域が抱える課題をデジタルでどこまで解決できるかに挑戦する計画骨子となり、会津若松市はその実証場所として動き出したと海老原氏は振り返った。
参考にしたのはデンマーク、スウェーデンの政策。EHR (生涯医療記録、電子カルテ)などデジタル駆使の医療体制をすでに作り上げていた両国は世界の研究者が集まる「メディコンバレー」として医療健康産業がGDPの2割を占めるまでに成長した。
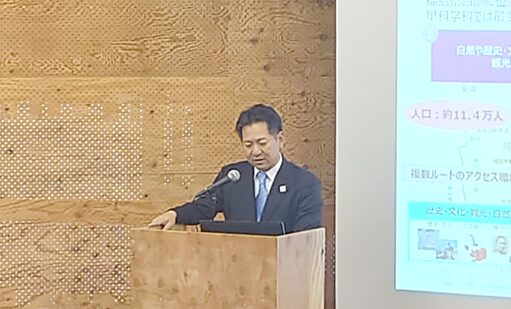
住民が使用のインセンティブもつサービスを創出
2011年6月に市、アクセンチュア、会津大学は連携協定を結び、スマートシティに着手。
次々と手を打つ中で、当初から海老原氏らが気を配っていたのが、「住民にデジタルサービスを使うインセンティブをもってもらうこと」(海老原氏)だった。
「インセンティブ施策」の例として2013年に市内の家庭にエネルギー管理システム(HEMS)計器を導入した「省エネ推進プロジェクト」がある。従来、データを集約する単位はメーカー単位で行っていたが、会津若松市の実験では、どのメーカー製の計器を入れていても時間ごとの消費電力や電気代を集計できる仕組みを構築し、実験に参加する家庭が、市内の平均値や効率的な利用をされている家庭の消費との差を「見える化」。
結果、電気の使い方見直しにつながり、最大27%の消費減が見られたケースもあった。
2015年にデータ基盤構築、市民3割が利用
また、市民ポータルサイト「会津若松+」は連携サービスを開発することで市内人口11万人に対して年度のユニークユーザー数14万人のサイトへ成長。
日本最初期の2015年に構築したデータ連携基盤を通じたデジタルサービスの充実ぶりは、全国でも指折りのもので、2024年8月末で3万超のID数を誇る。海老原氏は「10年かけて25のサービスをつくり、データの質量とID数が指数関数的に増え、ここまで至った」と述懐した。
96社が加盟する運営組織が地域マネジメント、14の取組
2019年にはICTオフィス「スマートシティAiCT」が開設され、首都圏など会津若松の市外から38社、市内から8社が同拠点内に入居した。
これら入居企業のほか、趣旨に賛同する企業群が設立した、スマートシティ運営・地域マネジメントを行う一般社団法人AiCTコンソーシアムには24年9月時点で96社が加盟。
14の官民ワーキンググループが地域・市民のためのソリューション設計に汗を流している。
信託に基づくデジタル三方良し「会津若松では共創」
会津若松スマートシティの目標は「市民によるオプトイン(信託)に基づくデジタル三方良しの地域社会をつくる」(海老原氏)こと。
三方良しとは、大企業とユーザーの「二方良し」に対する概念。二方良しでは、企業独自のプラットフォームを持つ大企業が生活の根幹となるサービスに広く深く浸透し、地域企業はその下請けとなってしまう。結果、ユーザーは大企業に自らのID・データ提供を行う構図となる。
「三方良し」では、「地域」がプラットフォーマーとなり、市民のためのサービスを提供する。市民はスマートシティにメリット、納得感を覚えるからこそ主体的に地域へデータを預け、地域と協力する地場企業は市民のための新しいデジタルサービス、個々の市民にパーソナライズされたサービスをつくる。
コンソーシアム加盟社は「市民が望む社会を実現するサービスを考える」「データはそもそも市民個人のものという前提の上で、オプトインを徹底する」といった10のルールを厳守。「会津若松で共創し、市外で競争する」ことができていると海老原氏は話した。
日本各地、海外に広がる会津モデル
ユニークな会津若松モデルは内閣府「デジタル田園都市国家構想」に22年度から24年度の3年連続で、最も難しいとされるType3に採択された。
また、モデルは福島県そして全国へと広がりを見せていると海老原氏は紹介した。11県39地域で導入が進み、福島県内では24年度で人口カバー率約7割の28市町村が利用している。
例えばヘルスケア領域では、電子カルテのデータや血圧、体重、活動量といった情報を統合して個人が見られるようにし、日々の生活習慣に反映してもらう「健康長寿」を目指す構想だ。会津若松での取り組みを元に国際協力機構(JICA)と東南アジア・ブータン政府がデータ連携基盤構築を行っている。
市民の幸福へ、やるべきことからつくるデジタルサービス
また、会津若松の農作物の需要・供給を可視化することで中間流通のコストや手間を省き、地産地消を促す「三方良し」の取り組みも進行中。
市民がウェルビーイングな生活を送れるようデータに基づいて「やるべきことからやっていく取り組みを進めている」として海老原氏は講演を結んだ。